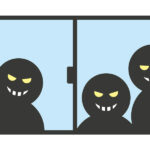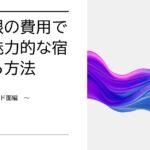2024年以降、コロナ禍からの回復と円安の影響を受け、訪日外国人観光客(インバウンド)は確かに増加傾向にあります。
しかし、これは必ずしも「観光業の安定した未来」を意味してはいません。
むしろ、観光業が持続的に成長していくためには、「インバウンドに頼りすぎない地域観光戦略」が不可欠です。
本コラムでは、地方の観光業が自立的かつ持続的に発展していくための戦略について、実務に役立つ視点から考察していきます。
1.なぜ「インバウンド頼み」では危ういのか?
観光業界では、「インバウンドが戻ってきたから安泰だ」との声を耳にすることが少なくありません。
観光業界では、団体旅行の縮小、バス料金の高騰、OTAの活躍といった“新たな構造変化”により、インバウンドに依存しがちです。
しかし、インバウンドは【為替・政情・感染症・国際関係】などの外的要因に大きく左右される不安定な市場です。
インバウンドに依存しすぎるのは非常にリスクが高いことがわかります。
観光業の本質的な安定の鍵は「地域住民や国内客からの支持を得る」ことにあります。
2.地域に根ざす「着地型観光」という選択肢
従来の旅行商品は、大都市(東京・大阪)発の周遊型ツアーが主流でした。
しかし、最近注目されているのが、「現地集合・現地発着」型の着地型観光です。
これは、地域の人々が自ら企画し、ガイドし、サービスを提供する「地元密着型ツアー」のことです。
たとえば京都では、観光客向けに地域の人が案内する着地型観光が成果を上げており、そのヒントとなったのは「地元の方の一言」だったといいます。
こうした観光は、ただ「モノを見る」から「地域での体験を通じた学びと感動」に変化しています。
3.地域観光に必要なのは「ストーリー」と「一貫性」
差別化の鍵は、単なる観光資源ではなく「地域独自のストーリー」です。
楠木建氏の『ストーリーとしての競争戦略』によれば、戦略は「数字の羅列」ではなく「筋の通ったストーリー」であるべきだとされます。
観光業にも同じことが言えます。
つまり、地域に伝わる文化・歴史・食・人柄などを丁寧に紡いでいくことが観光客の心を動かすのです。
たとえば、
- 「なぜこの地域に来るべきなのか?」
- 「ここでしか体験できないことは何か?」
といった問いに答えられることが重要です。
4.インバウンドと地域観光は両立できる
「インバウンドを完全に手放すべき」という話ではありません。
重要なのは、インバウンド客にも「地域に根ざした観光」を提供することです。
特にアジア圏からの訪日客は「雪景色」「牧場」「食」など日本らしい非日常に高い関心を持っており、これはまさに地方が持つ資源そのものです。
これらを地域資源として丁寧に磨き、外国語対応やSNS発信などを活用して発信すれば、単価の高い、リピーターになり得るインバウンド客を惹きつけることが可能です。
5.地域のプレイヤーが連携する「観光経営」のすすめ
観光は単なるレジャーではなく、地域経済のエンジンです。
そのためには、観光業者だけでなく、宿泊業、飲食業、交通、土産物店、自治体などが一体となって地域をブランド化していく必要があります。
『流れの整理だけで会社が良くなる魔法の手順』で述べられるように、企業活動においては“関係資産”が重要です。
地域観光も同じで、異業種連携によって“地域ぐるみの魅力”が形成されるのです。
6.観光経営を支える「見えない資産」とは?
観光業では「目に見える資源(観光地・施設)」に注目が集まりがちですが、実は“見えない資産”――スタッフの対応、地域住民のホスピタリティ、信頼関係、口コミなど――こそがリピーター創出や高評価レビューを支えています。
特に「最初の10秒でお客様を笑顔にする」接客や、「ワクワク体験」を演出するマーケティングは、競合他社と明確に差別化する大きな武器です。
まとめ:地域に根ざす観光戦略は「持続可能性」を育てる
インバウンドバブルはいつか終わりがきます。しかし、地域の暮らしに根ざし、地元住民と観光客がともに楽しめる観光は、「地域に愛され、持続可能な観光業」を育てます。
そのためには、
- 自社(自地域)ならではの強みを言語化し
- お客様との関係性を深め
- 地域全体で戦略的に価値を提供する
という視点が欠かせません。